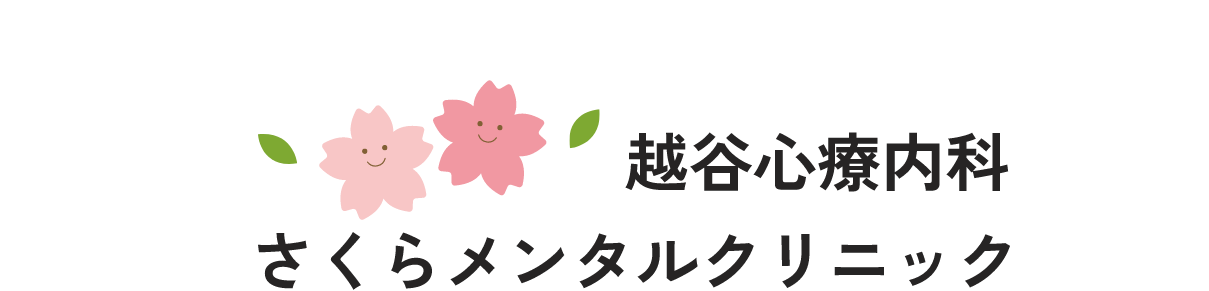南越谷駅徒歩1分
越谷心療内科
さくらメンタルクリニックの
クリニックブログ
パーソナリティ障害とは?
2025.06.10 2026.02.19
メンタルヘルス辞典
パーソナリティ障害とは、その人の思考、感情、対人関係、衝動のコントロールといった面において、多くの人が持っているものとは著しく異なるパターンが認められ、そのために社会生活や人間関係に大きな支障が生じている状態を指します。単なる個性や性格の偏りを超え、本人や周囲の人々が苦しむ状況が慢性的に続くことが特徴です。
パーソナリティ障害の理解:単なる「性格」ではない
「性格が悪い」といった言葉で片付けられがちなパーソナリティ障害ですが、これは表面的な行動だけを見て判断するべきではありません。パーソナリティ障害の根底には、幼少期の経験、遺伝的要因、脳機能の偏りなど、様々な複雑な要因が絡み合っています。そのため、本人の努力だけで簡単に改善できるものではなく、専門的な理解と適切なサポートが必要になります。
パーソナリティ障害は、大きくA群、B群、C群の3つのクラスターに分類されます。それぞれのクラスターには、いくつかの具体的なパーソナリティ障害が含まれます。
A群:奇妙で風変わりなパーソナリティ障害
- 妄想性パーソナリティ障害: 他者を不当に疑い、信用できないと感じる傾向が強いです。悪意を持った陰謀を企てられていると信じ込んだり、ちょっとした言動を悪意のあるものだと解釈したりすることがあります。
- シゾイドパーソナリティ障害: 他者との親密な関係を望まず、感情表現が乏しい傾向があります。一人でいることを好み、喜びや悲しみをほとんど感じないように見えます。
- 統合失調型パーソナリティ障害: 奇妙な思考や行動、独特な話し方を特徴とします。幻覚や妄想といった統合失調症の症状に似たものが見られることもありますが、統合失調症とは異なり、現実検討能力は比較的保たれています。
B群:感情的でドラマティック、移り気なパーソナリティ障害
- 反社会性パーソナリティ障害: 他者の権利を無視し、社会的な規範や法律を破る傾向があります。衝動的で無責任な行動を繰り返し、罪悪感や後悔を感じにくいことが特徴です。
- 境界性パーソナリティ障害: 対人関係、自己像、感情、行動において不安定さが見られます。見捨てられ不安が強く、感情の起伏が激しく、衝動的な自傷行為や薬物乱用などが見られることもあります。
- 演技性パーソナリティ障害: 過度に感情的で、注目を集めることを強く求める傾向があります。服装や言動で自分を魅力的に見せようとし、ドラマティックな振る舞いをすることが多いです。
- 自己愛性パーソナリティ障害: 誇大な自己評価を持ち、賞賛を強く求め、他者への共感が欠如していることが特徴です。自分は特別であると考え、他者を利用したり、見下したりすることがあります。
C群:不安で恐れを感じやすいパーソナリティ障害
- 回避性パーソナリティ障害: 批判や拒絶を恐れ、対人関係を避ける傾向があります。自分に自信がなく、人との交流を望んでいても、傷つくことを恐れて踏み出せないことが多いです。
- 依存性パーソナリティ障害: 他者に過度に依存し、自分一人では何も決められないと感じる傾向があります。見捨てられることを恐れ、他者の意見に流されやすく、不当な要求にも応じてしまうことがあります。
- 強迫性パーソナリティ障害: 完璧主義で、秩序や規則にこだわりすぎる傾向があります。融通が利かず、完璧を求めるあまり、物事をなかなか終わらせることができないことがあります。
診断と治療のプロセス
パーソナリティ障害の診断は、精神科医や臨床心理士などの専門家が行います。診断には、本人の生育歴、現在の生活状況、対人関係のパターン、思考や感情の特徴などを詳しく聞き取り、場合によっては心理検査を行うこともあります。単一の症状だけで判断するのではなく、長期的なパターンや本人の苦痛の程度を総合的に評価します。
治療の中心となるのは、精神療法です。特に、認知行動療法や弁証法的行動療法(DBT)は、パーソナリティ障害の治療に有効であることが示されています。これらの療法では、自分の思考パターンや行動の癖を認識し、より適応的な方法を学ぶことを目指します。また、必要に応じて、感情の不安定さや衝動性をコントロールするために、薬物療法が併用されることもあります。
周囲の理解とサポートの重要性
パーソナリティ障害は、本人だけでなく、その家族や友人といった周囲の人々も大きな影響を受けます。特に、境界性パーソナリティ障害などは、感情の波が激しいため、周囲の人々も疲弊してしまうことがあります。しかし、パーソナリティ障害は本人の「わがまま」や「性格の悪さ」で片付けられるものではなく、本人が苦しんでいる状態であるという理解が重要です。
周囲ができることとして、まずは病気について正しく理解すること、そして、本人の苦しみに寄り添い、サポートを提供することが挙げられます。感情的な巻き込まれを避けつつ、適切な距離感を保ちながら、専門家への受診を促すことも重要です。また、家族向けのサポートグループやカウンセリングも有効な場合があります。
まとめ
パーソナリティ障害は、多様なタイプがあり、その症状も人それぞれです。しかし、共通しているのは、その人の思考や感情、対人関係のパターンが社会生活に支障をきたし、本人や周囲が苦しんでいるという点です。単なる性格の問題と捉えず、専門家による適切な診断と治療を受けることで、症状の改善や生活の質の向上が期待できます。パーソナリティ障害への理解を深め、偏見をなくすことで、本人たちが安心してサポートを受けられる社会になることが望まれます。
監修者
根木 淳代表医師
愛知県生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、大手金融機関に勤務。2005年、秋田大学医学部卒業後、名古屋市立大学医学部精神科に入局。八事病院、三重県立子ども心身発達医療センターなどで研鑽を積む。京都大学医学部大学院とfMRIによる精神症状の脳機能の共同研究を経て慶應義塾大学大学院精神・神経科に入局。東京大学工学系研究科と連携して自動車運転の認知機能と安全性についての研究を行う。大学病院での診療、戸田病院、秋元病院、ガーデンクリニックなどでの診療業務に併行して、外資系及び国内大手IT企業、外資系大手コンサルティングファーム、テレビ・インターネット通販企業、都市銀行、国内大手証券会社、総合商社、特許翻訳・知財コンサル系企業、建設コンサルタント企業、広告代理店、大手旅行代理店、独立行政法人(公的法務支援機関)、大手不動産、大手企業信用調査会社、グローバルEC系企業、大手アパレル企業、国内最大手スーパーなど、都心大企業を中心に50社以上の産業医として企業のメンタルヘルスに従事。令和2年5月、北越谷駅前さくらメンタルクリニック院長に就任。併行して産業医業務に従事している。
【資格・所属学会など】
日本精神神経学会専門医・指導医
精神保健指定医
日本医師会認定産業医
日本老年精神医学会専門医・指導医