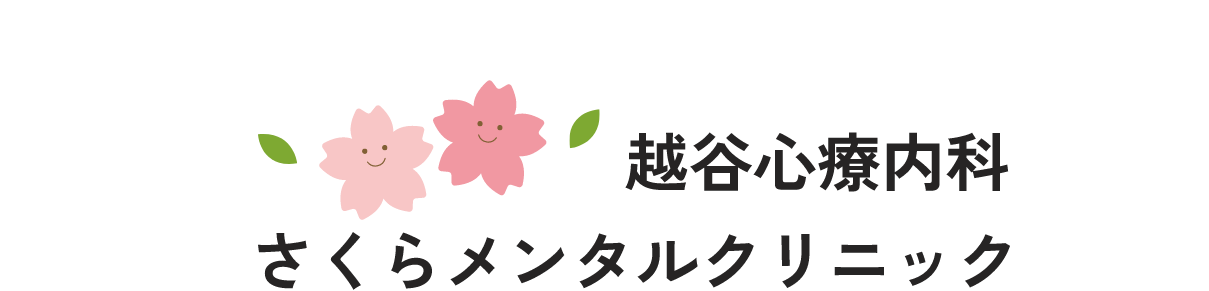南越谷駅徒歩1分
越谷心療内科
さくらメンタルクリニックの
クリニックブログ
発達障害からニューロダイバーシティ(神経多様性)へ
2025.10.15 2025.11.07
院長のつぶやき
発達障害という言葉はずいぶん浸透してきましたが、それが何かという具体的なイメージを持ってらっしゃる方は、まだ少ないかもしれません。
私が持っているイメージは、天に与えられた才能を持って生まれた方、というイメージです。そして、その多くの方は、発達障害とは気づかずに、社会に適応して、普通に働き、普通に暮らしていますし、会社の経営者には発達障害の人が多いとも言われています。
DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)が改訂され自閉症に「スペクトラム」という概念が導入されてから、程度の違いはそれぞれですが、全体で見ると普通の人たちからの連続であるという認識がますます広まってきています。つまり、「障害」という言葉が持つイメージとはまったく違うのです。その反省から、DSM-5の日本語訳では、「○○障害」という診断名をやめて、「○○症」という名前に変わっています。「発達障害」は、正式には「神経発達症」という名前に変わっています。
さらに、「障害」ではなく「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」と捉える活動も広まってきています。経済産業省もニューロダイバーシティの概念を推進しており、「発達障害のある人が持つ特性(発達特性)を活かし活躍いただける社会を目指します」としています※。
一方で、残念ながら発達障害の方の苦手な部分ばかりが注目され、生きづらさを抱えて、心療内科受診や検査を受けることを考えておられる方もいらっしゃるでしょう。恐れずに一歩を踏み出してみたら、今よりご自身に合う環境で、ストレスの少ない暮らしができるようになるかもしれません。発達特性があるからこそ、その可能性を秘めているのではないでしょうか。
監修者
院長 村重直子
当院は埼玉県越谷市の南越谷駅から徒歩1分、新越谷駅から徒歩2分という立地で、うつ病、不安障害、パニック障害、不眠症、適応障害、児童・思春期のメンタルケアまで幅広く対応し、一人ひとりを大切に診療に当たっております。
私はこれまで、ニューヨークのベス・イスラエル・メディカルセンター、国立がんセンター中央病院、および複数のクリニック・訪問診療に携わり、国内外で多様なライフステージに応じた医療に従事してまいりました。
一人ひとりに寄り添い、その方の人生に伴走する医師でありたいと願って診療しています。
特に児童精神科・思春期のメンタルケアでは、一人の母親としても共感を持ちながら、お子さんの「過去・現在・未来」を一緒に考えてまいりましょう。思春期ではご本人の意思を尊重し、必要に応じて親御さんと別々の時間を設けることもございます。すべては、将来、お子さんの持つ可能性が花開く時のために。
心の不調でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。越谷市を中心に、地域の皆様の頼れる診療所として、スタッフ一同、誠意をもって診療にあたります。