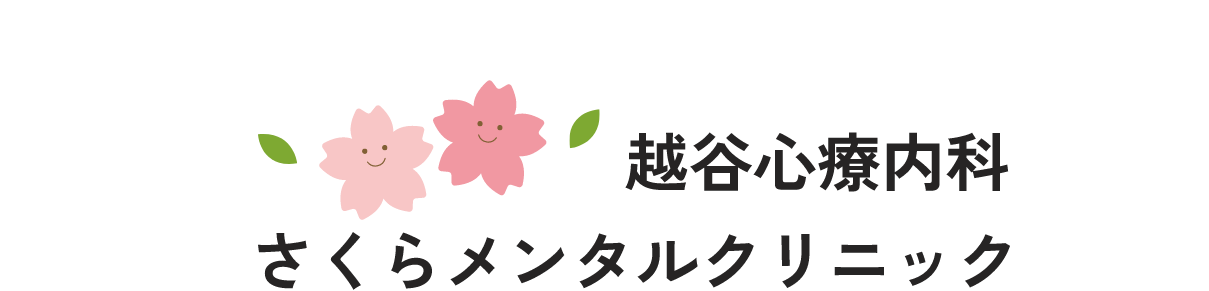児童精神科とは?
児童精神科は、子どもから思春期のこころの悩みや発達の特性に寄り添い、医学的に評価・支援を行う専門分野です。ことばや行動、感情のあらわれ方には一人ひとり違いがありますが、成長の過程で現れる困りごとが、家族や学校生活に影響を与えることもあります。
児童精神科では、こうしたこころのサインに早く気づき、正確に見きわめたうえで、必要に応じて治療・環境調整・心理支援を行います。発達の特性と向き合いながら、その子らしい歩みを支えることを目指します。
このようなことでお悩みの方はご相談ください
以下のような症状や状態が当てはまる方は、児童精神科へご相談ください。
このような場合はご相談ください
- 集団生活になじめず、学校や園で困っている
- おしゃべりや身ぶりに違和感がある
- こだわりが強く、切り替えが苦手
- 落ち着きがなく、じっとしていられない
- 指示が通りにくく、集団行動が苦手
- 眠れない、朝起きられない
- 食べものの好みが極端すぎる
- ちょっとしたことでかんしゃくを起こす
- 自分を責めたり、消えてしまいたいと口にする
- チックのような動きや声が出る
- 親子関係で悩んでいる
- 医師や学校、保健師から受診をすすめられた
児童精神科で扱う主な診療内容
児童精神科で扱う主な診療内容をご紹介します。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 限局性学習症(LD)
- チック症/トゥレット症候群
- 不登校・起立性調節障害
- 児童期うつ病・不安症
- 選択性緘黙
- 愛着障害
- 摂食障害(神経性やせ症・過食症など)
- 発達性協調運動障害(DCD)
- 強迫症(児童期)
- PTSD/トラウマ反応
児童精神科の各症状の主な原因
児童精神科の各症状の主な原因を紹介します。
1.自閉スペクトラム症(ASD)
脳の情報処理の仕組みや社会的認知にかかわる神経回路に偏りがあるとされています。遺伝的な要素が強く、家庭環境や育て方が直接の原因ではありません(Ecker et al., Lancet Neurol, 2015)。
2.注意欠如・多動症(ADHD)
ドパミン系の神経伝達や前頭前野の働きの偏りが関係しています。遺伝的な影響が強く、環境要因や養育の問題では説明できません(Faraone et al., Nat Rev Dis Primers, 2015)。
3.限局性学習症(LD)
読む・書く・計算するなど特定の学習機能に限って困難があり、脳の特定領域の情報処理の違いによるものと考えられています(Shaywitz et al., Biol Psychiatry, 2008)。
4.チック症/トゥレット症候群
脳内のドパミン系や皮質-線条体-視床回路の調整機構に関係があるとされています。遺伝的要因とストレスの影響が複雑に絡みます。
5.不登校・起立性調節障害
体の自律神経機能の乱れと、学校生活への不安や対人関係のストレスが重なって起こることが多いとされています(文科省・小児科学会合同調査)。
6.児童期うつ病・不安症
ストレスや家庭・学校環境の影響を背景に、脳内のセロトニンなどの神経伝達系の乱れが関係することが知られています。
7.選択性緘黙
安心できる場所では話せるのに、特定の場面(学校など)で話せなくなる症状です。不安傾向や気質的な要因が強く関与します。
8.愛着障害
幼少期の親子関係における一貫性のない対応、虐待やネグレクトなどが原因となることがあります。安全基地が形成されにくいことが背景にあります。
9.摂食障害
自尊感情の揺らぎや社会的な圧力、過度な完璧主義傾向などが背景にあり、脳内報酬系の異常も示唆されています。
10.発達性協調運動障害(DCD)
運動計画・実行にかかわる神経系の機能が未熟または偏りがあることが原因とされています。知的発達とは関係しません。
11.強迫症(児童期)
脳の制御回路(前頭前野と線条体)の過活動や、セロトニン系の異常が背景にあります。家族性も報告されています。
12.PTSD/トラウマ反応
自然災害・事故・暴力などによる強い恐怖体験が脳に記憶され、神経系が過敏になることで症状が出ると考えられています。
児童精神科の各診療内容における治療法
各診療内容における治療法をご紹介します。
1.ASD
構造化支援やソーシャルスキルトレーニング(SST)、環境調整が中心。薬物は二次症状(不安・衝動)に応じて使用。
2.ADHD
薬物療法(メチルフェニデート、アトモキセチン)と行動療法の併用が標準治療。時間管理や情緒調整の支援も重要。
3.LD
学習支援(特別支援教育)、音読支援、ICTの活用など。本人の得意を活かす工夫が治療の中心。
4.チック症
軽症例は経過観察。重度には行動療法やドパミン拮抗薬が用いられます。ストレス管理が大切です。
5.不登校・起立性障害
生活リズムの整備、学校との連携支援、自律神経調整薬の使用。心理的支援も並行して行います。
6.児童期うつ病・不安症
支持的精神療法、認知行動療法(CBT)、必要に応じて抗うつ薬を慎重に使用します。
7.選択性緘黙
段階的な不安場面への慣れ(曝露)、遊びを取り入れた関係づくり。家族支援が重要です。
8.愛着障害
心理療法(プレイセラピー等)、家族への支援、安心できる人間関係の回復を目的とします。
9.摂食障害
栄養管理と並行して、家族療法・個人心理療法を行います。重度の場合は入院が必要なことも。
10.DCD
作業療法士による運動プログラム、学校・家庭での支援調整が中心。本人の成功体験を重ねる工夫が効果的。
11.強迫症
曝露反応妨害法(ERP)を基本とする認知行動療法が第一選択。必要に応じてSSRIを使用します。
12.PTSD/トラウマ
トラウマ焦点型CBT(TF-CBT)、安全な関係性の構築、プレイセラピー。急性期には薬の使用も検討。