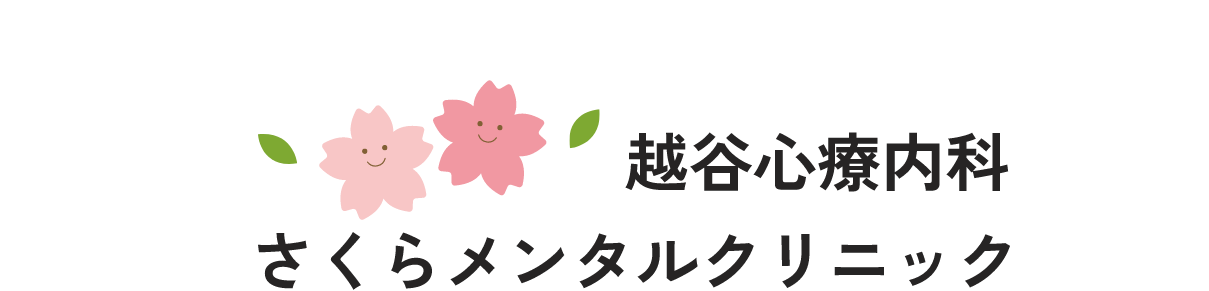南越谷駅徒歩1分
越谷心療内科
さくらメンタルクリニックの
クリニックブログ
心療内科受診と傷病手当金。安心して療養するためのサポートガイド
2025.06.10 2025.10.26
心療内科について
仕事や日常生活において心身の不調を感じ、心療内科の受診を検討している方も少なくないでしょう。精神的な不調が原因で仕事を休むことになった場合、経済的な不安を抱えるかもしれません。そのような時に知っておきたいのが「傷病手当金」の制度です。
傷病手当金は、病気やケガで働けない状態になった被保険者の生活を保障するための重要な制度です。心療内科で診断される適応障害やうつ病、不安障害などの精神疾患も、傷病手当金の支給対象となる場合があります。この記事では、心療内科を受診しながら傷病手当金を受給するための具体的な方法や注意点について詳しく解説します。
傷病手当金とは?その目的と支給要件
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休んだ際に、生活費を保障するために支給される手当です。特に精神的な不調は、周囲に理解されにくいこともあり、経済的な支援は安心して療養に専念するために不可欠な要素となります。
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
業務外の病気やケガによる療養のための休業であること
業務中や通勤中に生じた病気やケガは、労働災害保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です。心療内科で診断される精神疾患は、多くの場合、この「業務外」に該当します。
仕事に就くことができない状態であること
医師の診断に基づき、現在の仕事内容を遂行できない状態であると判断される必要があります。自己判断ではなく、医師の意見書が重要です。
連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
「待期期間」と呼ばれる連続する3日間の休業が必要です。この3日間には、有給休暇、土日、祝日などの公休日も含まれます。待期期間が完成すると、4日目以降の休業から支給対象となります。
休職期間中に給与の支払いがない、または給与が傷病手当金の金額より少ないこと
休業中に会社から給与が支払われている場合、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、給与額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
心療内科受診から傷病手当金申請までの流れ
心療内科を受診し、傷病手当金を申請するまでの一般的な流れは以下の通りです。
ステップ1:心療内科を受診し、医師に相談する
体調に異変を感じたら、まずは心療内科を受診しましょう。医師の診察を受け、診断名や病状、休職の必要性について相談します。この際、傷病手当金の申請を考えている旨を医師に伝えることが重要です。医師は、診断書や意見書に病名、初診日、症状の経過、治療内容、休職の期間などを記載します。
ステップ2:会社に休職と傷病手当金申請の相談をする
医師から休職が必要と判断されたら、速やかに会社の担当者(人事部、総務部、直属の上司など)に休職の意向と、傷病手当金の申請を検討していることを伝えます。会社によっては、休職に関する手続きや、傷病手当金の申請書類の取り寄せ方法が異なる場合があります。必要な書類の確認や、会社側の証明(事業主の証明書)について相談しましょう。
ステップ3:傷病手当金支給申請書を入手し、記入する
傷病手当金支給申請書は、ご自身の加入している健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトからダウンロードするか、会社の担当部署を通じて入手できます。申請書には、本人記入欄、担当医師記入欄、会社記入欄があります。
- 本人記入欄: 氏名、住所、振込先口座、マイナンバーなどの個人情報を正確に記入します。傷病名については、医師が記載した内容を転記しましょう。
- 担当医師記入欄: 心療内科の医師に記入を依頼します。医師は、病名、初診日、病状、治療経過、労務不能と認められる期間、今後の治療方針などを詳細に記載します。
- 会社記入欄: 会社の担当者が、勤務状況、休職の理由、給与の支払い状況などを証明する内容を記入します。
ステップ4:必要書類を揃えて提出する
傷病手当金支給申請書が全て記入されたら、以下の必要書類を揃えて、ご自身の健康保険組合または協会けんぽの支部へ提出します。
- 傷病手当金支給申請書
- 医師の意見書(診断書)
- 事業主の証明書
- 振込先口座の通帳のコピー(通常は不要な場合が多いですが、念のため確認しましょう)
提出方法は、郵送、窓口への直接持参、会社経由などがあります。会社の担当者に確認することをおすすめします。
傷病手当金を受給する上での注意点
傷病手当金は、療養を支援する大切な制度ですが、受給にあたっていくつか注意すべき点があります。
定期的な通院が必要
傷病手当金の支給を継続するためには、原則として月に1~2回程度の定期的な通院が必要です。医師は、申請期間中の診察に基づいて労務不能の状態であることを証明します。診察がない月は、医師が申請書に記載できないため、手当が支給されない可能性があります。体調が回復してきたとしても、定期的な受診を怠らないようにしましょう。
初診日以前の期間は対象外
傷病手当金は、医師が労務不能と判断した日、つまり医療機関に初めてかかった日(初診日)以降が対象となります。会社を休んでからしばらく経って受診した場合、初診日より前の休んでいた期間は申請対象外となるため、早めの受診が大切です。
診断書の記載内容と手数料
傷病手当金の申請書に医師が記入する意見書(診断書)には、病名、症状、休職期間などが具体的に記載されます。診断書作成には文書料が発生し、一般的には保険診療で300円程度の自己負担が生じます。
支給期間と金額
傷病手当金の支給期間は、支給が始まった日から通算して最長で1年6ヶ月です。支給金額は、休業開始日以前の直近12ヶ月の標準報酬月額(給与を等級に分けた基準額)を平均した額の3分の2程度が目安となります。正確な金額は、以下の計算式で算出されます。
(支給開始前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額) ÷ 30日 × 2/3 = 傷病手当金の支給日額
例えば、平均月収が30万円の場合、1日あたり約6,667円が支給され、1ヶ月で約20万円が支給される計算になります。
退職後の継続受給
会社を退職した場合でも、一定の条件を満たせば傷病手当金を継続して受給できる可能性があります。具体的には、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること、および退職日に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていることが必要です。ただし、退職日に出勤してしまうと継続受給の条件を満たせなくなる場合があるため、注意が必要です。
安心して療養に専念するために
心身の不調で仕事ができない状態は、精神的にも経済的にも大きな負担となります。傷病手当金は、そのような状況にある被保険者をサポートするための重要な制度です。心療内科を受診し、医師の適切な診断とサポートを受けながら、傷病手当金を活用して安心して療養に専念することが、回復への近道となります。
もし、申請手続きに関して不明な点があれば、ご自身の健康保険組合や会社の担当部署に遠慮なく相談しましょう。適切な制度を活用し、心身の健康を取り戻すことに集中してください。
監修者
根木 淳代表医師
愛知県生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、大手金融機関に勤務。2005年、秋田大学医学部卒業後、名古屋市立大学医学部精神科に入局。八事病院、三重県立子ども心身発達医療センターなどで研鑽を積む。京都大学医学部大学院とfMRIによる精神症状の脳機能の共同研究を経て慶應義塾大学大学院精神・神経科に入局。東京大学工学系研究科と連携して自動車運転の認知機能と安全性についての研究を行う。大学病院での診療、戸田病院、秋元病院、ガーデンクリニックなどでの診療業務に併行して、外資系及び国内大手IT企業、外資系大手コンサルティングファーム、テレビ・インターネット通販企業、都市銀行、国内大手証券会社、総合商社、特許翻訳・知財コンサル系企業、建設コンサルタント企業、広告代理店、大手旅行代理店、独立行政法人(公的法務支援機関)、大手不動産、大手企業信用調査会社、グローバルEC系企業、大手アパレル企業、国内最大手スーパーなど、都心大企業を中心に50社以上の産業医として企業のメンタルヘルスに従事。令和2年5月、北越谷駅前さくらメンタルクリニック院長に就任。併行して産業医業務に従事している。
【資格・所属学会など】
日本精神神経学会専門医・指導医
精神保健指定医
日本医師会認定産業医
日本老年精神医学会専門医・指導医