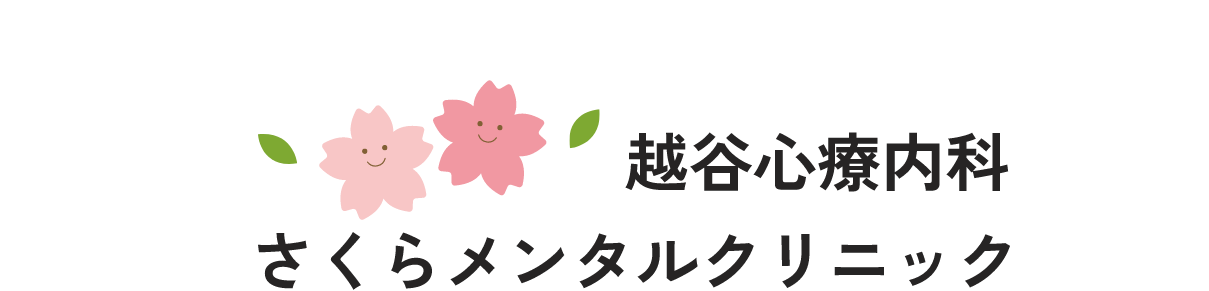南越谷駅徒歩1分
越谷心療内科
さくらメンタルクリニックの
クリニックブログ
「教育虐待」にならないよう、学習障害(LD、ディスレクシア)に気づいてあげましょう
2025.10.26 2025.11.07
院長のつぶやき
学習障害のお子さんには、個々の違いはありますが、学校で採用されている通常の学習方法とは違う方法で教えてあげる必要があります。認知の仕方が、通常の方法とは異なるので、それぞれのお子さんに合う学習方法を模索することになるのです。
ところが、お子さんの周囲の大人たちがディスレクシアと気づいてあげられなかったら、どうなるでしょう?大人たちは、学校や塾の通常の学習方法のまま、良かれと思って「がんばれ、がんばれ」と学習量を増やしたりして、学校や塾の他の子たちと同じことを同じ方法でできるようになることを求めます。これは、大人にとっても並大抵の努力でできることではありません。お子さんに愛情を注ぎ、将来を案ずればこそ可能な、尊い努力です。
その一方で、これがお子さんにとってどういう状況か、想像できるでしょうか?お子さんは、学校で他の子たちがすんなりできることが自分にはできないという現実を一番よく知っていて、失敗体験の繰り返しや強い劣等感からくる不安感を持っています。さらにその上、やってもわからない方法、やっても覚えられない方法を、ただでさえ他の子たちよりつらいのに、その何倍もやらされて、挙げ句の果てに「なんでこんなこともわからないの?」「他の子たちは終わってるのに、なんでそんなに時間かかるの?」といった言葉を浴びせられることが多いのです。
こうした日々が続いた結果、自尊心や自己肯定感が著しく低下し、ディスレクシアそのものではない、二次的な症状を引き起こします。あるお子さんは、こんなにダメな自分で、こんなにつらい毎日なら生きていたくないと思って「僕、死にたいんだよ」と言うかもしれません。引きこもりや不登校につながるかもしれません。「LD(学習障害)が疑われる例③」のように、人知れずリストカットしているかもしれません。またあるお子さんは、すべてに投げやりになって、非常に反抗的で攻撃的な態度をとり、イライラして、何を聞いても「知らん」とか「時間の無駄」としか答えなくなるかもしれません。
これまで誰にも理解してもらえずに、他の子たちより何倍もつらい勉強を、何倍も努力してきたお子さんたちの心情を考えると、胸がつぶれる思いです。
このように、大人たちがディスレクシアかどうか気づいてあげて、そのお子さんに合う学習方法を一緒に模索してあげられるかどうかが、お子さんの性格や人格形成に影響する可能性があります。 学習障害やディスレクシアという名前だけでなく、その症状(症例1、2、3、4)まで知っている人は、日本ではまだまだ少ないと言わざるを得ません。ディスレクシアの症状を、一人でも多くの方々に知っていただいて、こうしたお子さんたちを一日も早く見つけてあげられる社会になることを祈ってやみません。
監修者
院長 村重直子
当院は埼玉県越谷市の南越谷駅から徒歩1分、新越谷駅から徒歩2分という立地で、うつ病、不安障害、パニック障害、不眠症、適応障害、児童・思春期のメンタルケアまで幅広く対応し、一人ひとりを大切に診療に当たっております。
私はこれまで、ニューヨークのベス・イスラエル・メディカルセンター、国立がんセンター中央病院、および複数のクリニック・訪問診療に携わり、国内外で多様なライフステージに応じた医療に従事してまいりました。
一人ひとりに寄り添い、その方の人生に伴走する医師でありたいと願って診療しています。
特に児童精神科・思春期のメンタルケアでは、一人の母親としても共感を持ちながら、お子さんの「過去・現在・未来」を一緒に考えてまいりましょう。思春期ではご本人の意思を尊重し、必要に応じて親御さんと別々の時間を設けることもございます。すべては、将来、お子さんの持つ可能性が花開く時のために。
心の不調でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。越谷市を中心に、地域の皆様の頼れる診療所として、スタッフ一同、誠意をもって診療にあたります。